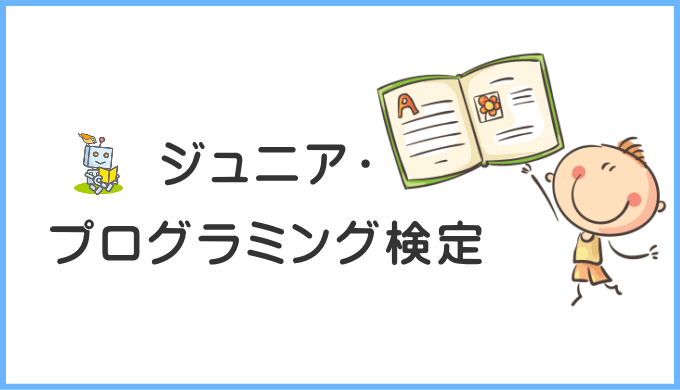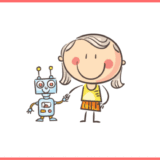もくじ
ジュニアプログラミング検定の特徴

ジュニア・プログラミング検定(Scratch部門)はサーティファイ 情報処理能力認定委員会が主催する子ども向けのプログラミング検定試験です。子ども向けとはいっても、受験資格に年齢制限がないので、誰でも受験することができます。
ジュニア・プログラミング検定の大きな特徴は自由な発想で実践的なプログラミングスキルを問われる検定であるということ。
他のScratch試験では、プログラミングが細切れになっており、1つの動作やブロック小単位の動きについて出題されることが多いです。
しかしジュニア・プログラミング検定の場合はお手本になる1つの動画を時間いっぱいかけてじっくり作りこんでいくという内容になっています。上位の級になると既に完成されたプログラムを修正する仕様変更の問題も出題されます。
つまり自分の書いたプログラムだけではなく、他人の書いたプログラムを読解し、修正するという能力が求められるわけです。
また、すべての級で製作したプログラムに自分のアレンジを加えてその仕様を説明するという「アレンジ問題」が出題されます。ただ問題を解くだけでなく、プログラミングに必要であるクリエイティブな発想を評価してくれる検定試験です。
関連ページ日商プログラミング検定とは?小学生から受験できるよ。
ジュニアプログラミング検定の勉強法

ジュニア・プログラミング検定向けの参考書「Scratchで楽しむ レッツ!プログラミング ジュニア・プログラミング検定 公式テキスト」が発売されているので、まずはこちらに沿って勉強を始めてみるとよいでしょう。
テキストはジュニア・プログラミング検定全レベルに対応したゲームを作っていくという内容です。
マンガが随所に挿入されており、小さい子でも楽しく学べるよう工夫がされていますよ。
ただし全レベルを網羅している分、Scratchを始めたばかりの子、もっと詳しく基本操作を知りたい子には少し大雑把な印象を受けるかもしれません。
そんな時はScratchを扱った別の入門書を先に読んでから公式テキストに戻ってくると理解が進みますよ。
関連ページキッズプログラミング検定とは?
ジュニアプログラミング検定(Scratch部門)の概要

【受験資格】
特になし
【受験料(税込)】
2020年3月までの受験
Entry(4級) 2,343円 Bronze(3級)2,546円 Silver(2級)2,750円 Gold(1級)2,954円
2020年4月以降の受験
Entry(4級)2,400円 Bronze(3級)2,600円 Silver(2級)2,800円 Gold(1級)3,000円
対象言語 Scratch(ヴァージョンは2.0および3.0に限定 1.4には対応していません)
【合格基準】
得点率60%以上
①問題文であたえられた条件を満たしたプログラムが組まれていること。
②自由なアイデアが盛り込まれていること。
(合格基準の引用元:https://www.sikaku.gr.jp/js/ks/point/)
【試験時間】
Entry(4級) 30分 Bronze(3級)・Silver(2級)40分 Gold(1級)50分
【試験会場】
個人受験 全国の随時試験会場(一部実施会場のない県あり)
【団体受験】
プログラミングスクール、学習塾、小学校などの教育機関で申請
条件を満たした会場
【試験日程】
会場により異なる
【主催団体】
サーティファイ 情報処理能力認定委員会
関連ページプログラミング教室は中学受験に役立つの?
メリット

ITスキルが身に付く
ジュニア・プログラミング検定の大きなメリットは実践的なプログラミングスキルが身に着く検定であるという点です。
小さな単位でブロックプログラムの意味を覚えても、それらを組み合わせて1つの作品を完成させていかなければ本当のプログラミング能力は養われません。
ジュニア・プログラミング検定では1つの作品を試験時間いっぱいをかけて作っていくので、1からオリジナルのプログラムを組む力を自然と身につけて行くことができますよ。
また実際に遊べそうなゲーム等が題材になっていますので検定試験の勉強という堅苦しいイメージを超えて楽しく勉強することができそうです。
検定試験に合格する実力が付けば、その知識をもとにオリジナルのゲームをScratch上に公開することもできるでしょう。
クリエイティブ能力が身に付く
また、クリエイティブな能力を伸ばす「アレンジ問題」の存在も子どもの自由な発想を伸ばす役に立ちます。
答えが決まっている従来の学校試験形式を超え、多様な正解をもつ「アレンジ問題」は柔軟な発想力を持つ子どもの意欲を刺激してくれます。
独学でも目指せる
勉強環境の面でもメリットがあります。
実施主体のサーティファイ 情報処理能力認定委員は「Webクリエイター能力認定試験」や「Photoshop®クリエイター能力認定試験」、「報処理技術者能力認定試験」などパソコンに関する様々な能力試験を主催しており、プログラミング試験の実施実績を積み上げている団体です。
ジュニア・プログラミング検定のスタートも2016年12月と小学校のプログラミング教育義務化より数年先んじており、すでに3年の実績があります。
公式テキストが完備されている点など、他の子ども向けプログラミング検定に比べ勉強環境が整っているので、プログラミング教室に通っておらず自分で試験勉強をしなければならないという子どもでも受験しやすい検定試験になっています。
関連ページ中学受験と高校受験、どっちがよい?中学受験に向いているかどうか判断する基準とは
デメリット

つまずくと総崩れになりやすい
ジュニア・プログラミング検定は1つのプログラムを順序だてて作り上げていく試験です。
実際プログラミングの現場では知識1つ1つを問われるわけではなく、1つの作品としての出来が評価の対象になるのでこのような形式は非常に実践的です。
一方で1カ所で躓くと他の部分が総崩れになってしまうという危うさもあります。
例えば、問題が1問1答のような試験であれば、1つの問題が分からなくても、飛ばして次の問題に挑戦することができますし、総合的な点数が合格基準を上回っていれば1,2カ所全く手を付けていない問題があっても合格できます。
しかし、ジュニア・プログラミング検定の場合は、すべての問題が相互に関連しあっているので、気軽に飛ばしたり未回答にすることはできません。
もちろん合格基準は60%以上となっており、わからない箇所を飛ばしたり、ミスをしたりしても合格基準を上回っていれば合格は可能ですが、動作させてみてお手本と違うところが出てくればだれでも焦ってしまうものです。
1つの問題にこだわりすぎて、うまく切り替えができないということが起こりやすい検定形式といえます。
理系は得意だけど国語が苦手な子にはキツイ
また、ジュニア・プログラミング検定には「アレンジ問題」が出題されます。
この問題ではプログラミングのアレンジスキルとともに、どのようなアレンジを加えたか文章(もしくは絵)で説明するという能力が必要になります。
つまり国語力や表現力も評価対象になるということです。
この手の表現力を問う問題(感想文を書いたり、自由なテーマでのお絵かきなど)が苦手という子は苦手意識を感じてしまう可能性もあります。
既存のものをアレンジしたり自分の発想を表現したりという能力はまさにこれからの時代に必要な力です。
うちの子はこのような形式は苦手だから…で片づけてしまわず、発想力を延ばす契機ととらえ、挑戦してみることも大事かもしれません。
参考URL:https://www.sikaku.gr.jp/js/ks/
⇒プログラミングが大学入試にでる!大学入学共通テストに情報科目を導入予定。
ロボット・プログラミング関連の資格検定はほかにもあるよ↓