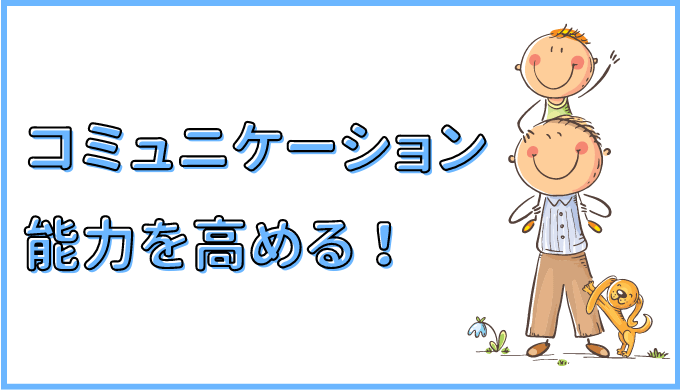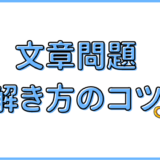コミュニケーション能力は、さまざまな人間関係を重ねることで学んでいくものです。しかし、社会の変化で子どもの人間関係が希薄化し、その結果、衝動的にキレたり、言いたいことが言えないなど、人間関係のトラブルが増えています。
コロナ禍で人と人の接触がさらに減っている今、コミュニケーション能力を高める方法を取り上げてみました。
ゲーム感覚で楽しく学べる
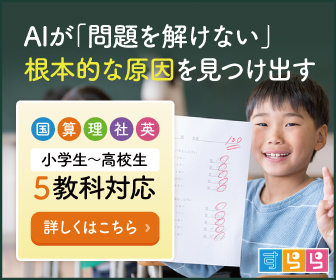
もくじ
数値化できないが大切な能力

知能指数や学力は数値で測ることができます。一方、コミュニケーション能力は数値化が困難です。このような能力を非認知能力と言います。数値化できないために、科学的な向上方法の解明が難しいとも言えます。
しかし、子どもが友達と仲良くするには、コミュニケーション能力が重要になります。大人になって就職する際に重視されるスキルが、コミュニケーション能力です。コミュニケーション能力は社会をうまく生き抜くために大切なスキルなのです。そんな人生を左右する能力を高める方法はあるのでしょうか?
関連ページ小学生の非認知能力は鍛えられる!具体的にどうしたらいいの?
アサーションという考え方

コミュニケーション能力を高める方法はいろいろ考案されています。その一つが、アサーション・トレーニングです。学校や企業でも取り入れられているアサーション・トレーニングについて紹介したいと思います。
アサーションは、「自分も相手も大切にするコミュニケーション」の方法です。
アサーションでは、コミュニケーションを3つタイプに分けます。「攻撃的(アグレッシブ)」「非主張的(ノンアサーティブ)」「アサーティブ」の3つです。
攻撃的(アグレッシブ)は、「自分を大切にするが、相手を大切にしない自己表現」です。自分が正しいという感情が強く、人の言い分を聞かずに、頭ごなしに主張します。
非主張的(ノンアサーティブ)は、「相手を大切にするが、自分を大切にしない自己表現」です。自信がなく、自分よりも周りの人のことを考え、それが相手に対する思いやりと考えます。
アサーティブは、「自分も相手も大切にする自己表現」です。お互いの意見が食い違った時には、攻撃的に相手を打ち負かしたり、非主張的に相手に合わせたりするのではなく、妥協点を探るコミュニケーションです。
関連ページ子どもの「自己表現」と「協調性」を上手に両立させる方法
アサーショントレーニング

3つのタイプの内、アサーティブなコミュニケーションができれば、うまく人間関係を築けそうですが、どのように身につければ良いのでしょうか?
アサーション・トレーニングでは、3つのタイプのシナリオを二人一組でロールプレイする方法がとられます。以下のようなシナリオが使われます。
これは、友達に貸したマンガの本を兄が読みたいと言い出したので、すぐに返してもらいたい時の会話です。
攻撃的(アグレッシブ)な会話
「この前の本、返せよ」
「えっ、何?」
「何がじゃないよ。貸しただろう」
「あー、忘れてただけだよ。そんなふうに言わなくても・・・」
「ふざけるなよ。」
非主張的(ノンアサーティブ)な会話
「あの・・・この前貸したマンガの本なんだけど・・・」
「あぁ、ゴメン忘れてた。今持ってないから、また今度でいい?」
「あ、うん、いつでもいいけど・・・」
「そう?悪いね」
「いや・・・こっちこそ」
アサーティブな会話
「この間、貸したマンガの本、今日返して欲しいんだけど」
「今日じゃなきゃ、だめ?」
「明日、兄さんがみたいって言ってるから、できれば今日返して欲しいんだ」
「ごめん、まだ読み終わってないんだ」
「じゃあ、明日の朝まで待つよ。どう?」
「ありがとう、それなら、大丈夫だよ」
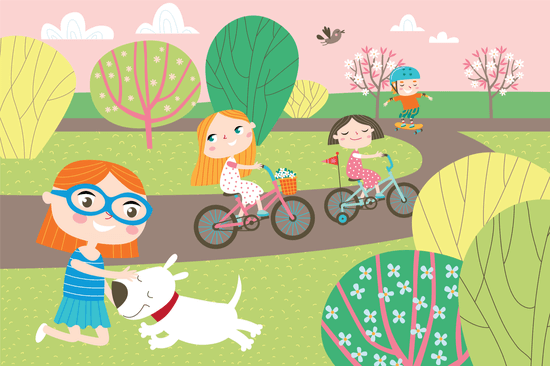
ロールプレイの後には、お互いが気持ち良い会話をするためには、どうすれば良いか話し合います。(1)
このシナリオを読んで、誰かイメージしなかったでしょうか?そうです、ドラえもんのジャイアン、のび太、しずかちゃんです。学校現場では、いばりやさん、おどおどさん、さわやかさんとも呼ばれます。
自分の主張だけしても、あるいは人の顔色を伺うだけでは、良いコミュニケーションとは言えません。お互いに考え方の違いや事情があることを想像し、折り合いをつけることが大切です。
また、誰もが3つのタイプの会話を多かれ少なかれ行っていることに気づくことも大事です。性格によって出やすい会話もあります。自分の性格や起こりやすい会話をあらかじめ知っておき、うまくコントロールができるようになれば、コミュニケーション能力は高まります。
アサーション・トレーニングはシンプルな方法に思えますが、それだけに子どもにも理解しやすい方法と言えるでしょう。
関連ページアンガーマネージメントとは?小学生にもできる感情をコントロールする訓練法。
アサーショントレーニングの効果研究
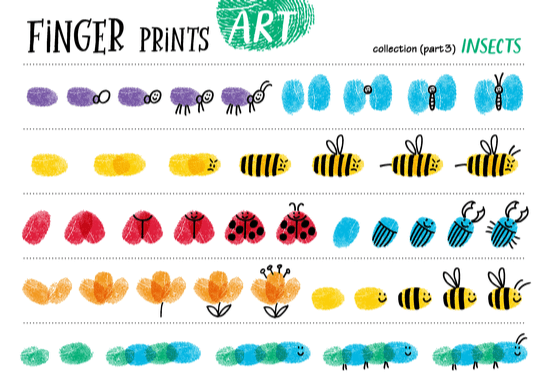
アサーション・トレーニングの効果を測定した研究があります。茨城県の公立小学校の4年生69名に45分間のセッションを10回実施し、効果測定が行われました。
その結果、アサーティブな会話が次第に増え、攻撃的な会話や非主張的な会話は次第に減少したことが明らかになりました。また、普段の学級生活の中で、「今の言い方、いばりやさんっぽくてやだな」というような会話が見られるようになったそうです。さらに、児童のストレスが減少したこともわかりました。(2)
家庭もコミュニケーション能力を高める場所
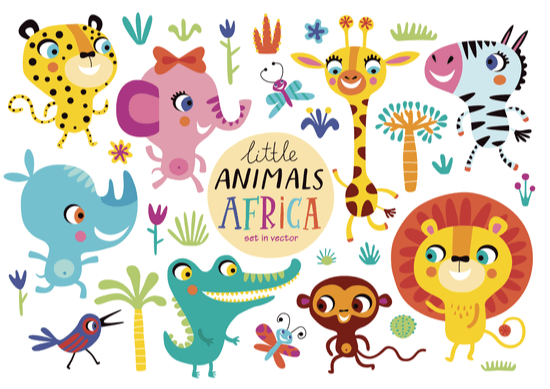
アサーション・トレーニングは、何度もくり返し練習することで、身につくものです。大切なことは、他人の気持ちを考えながら、自分の考えを言えるようになることです。
他人と意見が違ったときや、言いたいことがあるけど言いにくい時に、アサーションを思い出し、上手な断り方や優しい頼み方ができれば、良いコミュニケーションが生まれるでしょう。
アサーション・トレーニングに関しては、関連書籍もたくさんありますので、さまざまなトレーニング方法を参考にすれば、家庭もアサーションを身につける場所となります。そして、子どものコミュニケーション能力を高める中で、大人のコミュニケーション能力も向上することでしょう。
【参考文献】
(1)アサーション・トレーニング「3つの話し方」(茨城県教育委員会)https://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/shochu/shido/counselor/index.html
(2)渡部玲二郎・江幡綾子(2014年)「児童のコミュニケーション能力を高めるための実践研究(1)-小学校におけるアサーション・トレーニングの試み-」(茨城大学教育学部紀要64号)
(3)平木典子「アサーション入門 自分も相手も大切にする自己表現法」(講談社現代新書、2012年)
![]()
あっくんパパ
2児の父
京都大学大学院修了
博士(工学)